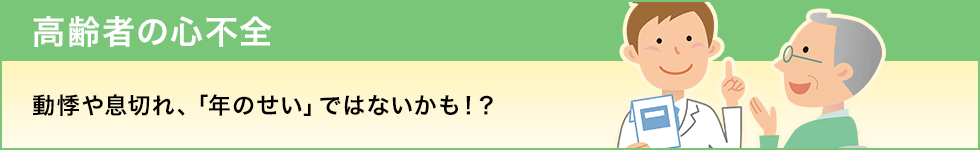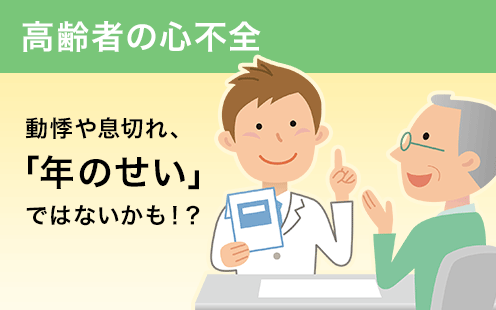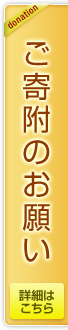講演5:動いて、元気な心臓へ!
運動を始めるための条件
私は心臓病の患者さんのリハビリを担当させていただいておりますが、患者さんからよくいただく質問に、「心臓病の人が運動して大丈夫でしょうか?」というものがあります。運動すると心臓に負担がかかるというイメージをお持ちの方は多いようです。そこでまずお伝えしているのが、「運動を始めるための条件がある」ということです。それは、①適切な治療が行われた状態であること、②症状が落ち着いていること、③医師の許可が出ていること、の3つです。その上で、「正しい方法」で運動することが重要となります。心臓病に対する運動療法の効果
この「正しい方法」についてお話ししていきたいと思いますが、まず心臓病に対する運動療法には様々な効果があることが、これまでの多くの研究によって実証されています。それをまとめると、①筋力や体力が向上し楽に動ける、②狭心症や心不全の症状(息切れ・疲れ易さなど)が軽くなる、③動脈硬化の危険因子である高血圧・脂質異常症・糖尿病などの生活習慣病が改善する(急性心筋梗塞や狭心症などの再発予防に繋がる)、④心臓病に伴う不安や抑うつ状態が改善する、⑤自律神経のバランスが良くなる、などが挙げられます。運動療法が、これらの心臓病に関わる様々な要因を改善することによって、「心臓病の方の生活の質や寿命の延長」につながることになります。心臓病における適切な運動とは?(運動の「強さ」)
では、心臓病の方における適切な運動とはどういったものを言うのでしょうか。まず問題となるのが運動の「強さ」です。強い運動ほど効果は高くなりますが、一方で傷害(心臓病の悪化、筋肉・関節の損傷など)の発生も増えていきます。逆に弱すぎる運動は、運動の効果が乏しくなります。そこで、一番良いのは障害の発生が少なく、かつ運動の効果が得られる強さの運動ということになり、それは「最大運動能力の中くらい(40~60%)の強さ」と言われています(図1)。運動の強さを調べる方法は色々ありますが、一番簡単なものは自覚症状によるボルグ指数と呼ばれるものです。これは、安静時の点数が6で、で点数の数字が大きくなるほど運動がきつい状態になります。先ほど述べた「最大運動能力の中くらい」の強さは、11(楽である)~13(ややきつい)に該当すると言われています(図2)。これは目安として、軽く汗ばむ・運動しながら会話ができる程度の状態となります。このように、運動中にご自分でどのくらいの症状を感じているかを意識することで、正しい強度で運動できているのかどうかを判断できます。
図1 心臓病における適切な運動の強さ
図2 自覚症状のチェックのしかた(ボルグ指数)
心臓病における適切な運動とは?(運動の「種類」)
続いて心臓病における適切な運動の「種類」ですが、これには主に有酸素運動と筋力トレーニングの2つがあります。有酸素運動というのは、簡単に言うと、苦しくない状態で持続的に運動ができる方法です。私たちがよく病院で使っているのが、歩行(トレッドミル:動くベルトの上を歩く)と自転車こぎ(自転車エルゴメータ)です。いずれも短時間の軽い運動から開始し、徐々に増加していきます。開始初期は5~10分を2セット、安定期は20~60分(短時間を分割して実施しても良い)を、少なくとも週3回以上、可能であれば心臓の状態に合わせて週5回まで増加します。ご自宅にはこのような機械はない方が多いと思いますが、先ほどご紹介した自覚症状に基づいて、外を歩くという方法でも十分効果は得られます。自宅でできる筋力トレーニング
次は筋力トレーニングについてです。当院ではマシンを使ってトレーニングする方が多いのですが、マシンを使用しなくてもトレーニングはできます。今回はご自宅でもできる簡単な運動をご紹介します。 まず運動に慣れていない方は、座った状態で、軽い負荷で運動を行うとよいでしょう。まず行いたいのは、つま先上げ、踵あげの運動です(図3A)。つま先上げは足のすねの筋肉の運動ですが、この筋力が落ちるとつま先が上にあがらなくなり、地面に足がひっかかったりする原因になります。踵あげは、ふくらはぎの筋肉の運動ですが、この筋肉は体を支えることのほかに、血液を心臓に返すためのポンプの働き(第二の心臓とも呼ばれる)もしています。運動の回数に関しては、1セットを10~20回とし、1~3セット程度を目安とします。この運動を含め、すべての運動において重要な点は、運動中に呼吸を止めないということです。呼吸を止めると、血圧が上昇して心臓の負担を増やす原因になります。呼吸は吸ったり吐いたりを繰り返しながら、運動していただきたいと思います。次に行っていただきたいのが、膝伸ばし、太もも上げです(図3B)。膝伸ばしは、太もも前面の筋肉(大腿四頭筋)の運動で、膝の筋肉が痛い方はこの筋肉が落ちている場合が多いです。少し深めに座り、膝をしっかりと最後まで伸ばすとともに、つま先をキュッと上に向けると、太ももの筋肉に力が入る感じがあると思います。太もも上げは、股関節前面の筋肉(腸腰筋)の運動で、ここの筋肉が落ちると腰が落ちて丸まったような姿勢になってしまいます。今度は少し浅めに腰掛けて、足が上がるところまでギュッとしっかり持ち上げると、股関節の付け根に力が入る感じが得られると思います。これらの運動も10~20回を1~3セット程度とし、やはり呼吸を止めないで行ってください。
続いて、座って行う運動が楽にできる方や、運動に慣れている方に行っていただきたい、立って行う運動です(図4)。これには、つま先立ち、立ち座りの運動があります。つま先立ちは、壁やテーブルに手を置いて、バランスを取り、ギュッと足の指(特に親指)で踏ん張りながら踵を持ち上げていただきます。これは、ふくらはぎの筋肉を強化する運動になりますが、先ほどの座って行う運動に比べると体重がかかるので、筋肉により強い負荷をかけることができます。立ち座りは、体を支える足全体の筋肉の運動です。スクワット運動と似ている動きですが、スクワット運動とは違って途中で止めずに座ってしまいます。これによってスクワット運動より少し軽い運動になります。上がるときは速く、下がるときはゆっくり行うことによって、負荷を強め、筋肉を強くする効果を高めることができます。この運動は、手すりやテーブルにつかまっても、何もつかまらなくても、どちらでも構いませんので、転ばずに、息切れが強くならない方法で行っていただきたいと思います。いずれも、5~10回を1~3セット程度、やはり呼吸を止めないように注意しながら行ってください。
図3A 自宅でできる筋力トレーニング:運動に慣れていない方
図3B 自宅でできる筋力トレーニング:運動に慣れていない方
図4 自宅でできる筋力トレーニング:運動に慣れてきた方
運動を始める前に必ずチェック!
いくつかの体操をご紹介しましたが、運動を始める前に必ずチェックしていただきたいことがあります。一つは薬を飲み忘れていないか、ということです。心臓の薬を飲まずに運動すると、運動中の心臓の負担が増加するからです。血圧が上がりすぎる、脈が速くなりすぎる、血液サラサラの効果が出ない、などといった状況で運動することになってしまいますので、運動の前に必ず薬の服用を済ませてください。そして、飲んでから30分程度あけてから運動を始めれば、安全に運動が行えると思います。もう一つは心臓病の悪化が疑われる所見はないか、ということです。悪化の所見がある時に運動すると、心臓病がさらに悪化する可能性があるからです。特に胸の痛み・圧迫感・動悸・息切れの増強などは要注意です。体重増加(1週間で2Kg以上)や手足のむくみの増強などは、心不全悪化のサインです。このように、心臓病の悪化が疑われる場合は、運動を控えて早めに受診しましょう。
より正確な運動を行うために:心肺運動負荷試験(CPX)
当院の外来で心臓リハビリテーションで運動療法を行っている方は、心肺運動負荷試験(CPX)という検査を受けています。これは口に検査用のマスクを付けて、血圧や心電図をチェックしながら、どんどん漕ぐのが重くなっていく自転車(エルゴメータ)を、頑張れるところまで漕いでいくという過酷な検査です。しかしこのCPX検査によって、どの程度の活動まで心臓が耐えられるのか、適切な運動の強さはどれくらいか、などが分かります。私たちはこの検査の結果をもとに、トレーニングや生活指導などを行っています。当院でCPX検査を受けたい方は、かかりつけ医に紹介状を作成していただき、循環器内科部長/心臓リハビリテーション室長の中山敦子医師の外来を予約なさってください。是非、ご相談していただければと思います。最後に本日のまとめになります(表1)。
表1 本日のまとめ