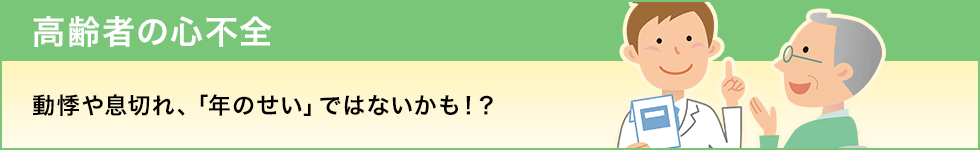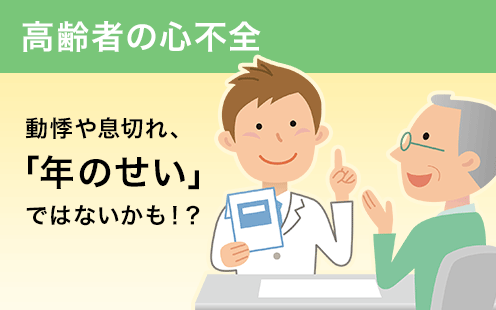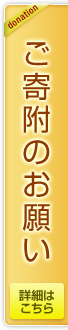生活習慣を工夫しよう:食事と運動
講演4:食べる力で心臓を守る
心臓に良い食事のポイント
心臓に良い食事のポイントは色々あると思いますが、中でも重要なのが「塩分を控える」ことと「バランスの良い食事を心がける」の二つです。本日はこの二点についてお話しさせていただきます。日本人の1日の食塩摂取量
日本人が1日にどの位の食塩を摂っているかに関しては、毎年行われている国民健康栄養調査によるデータがあります。令和5年の同調査によると、男性10~11g程度、女性8~9g程度となっています(図1)。高血圧・心不全・心筋梗塞などの予防を目標とした食塩摂取量は、皆さんも良くご存じの通り1日6g未満が目安です。実際の摂取量と目安量との間には3~5g程度の差があることになります。1食1gくらいずつの食塩を減らすと、目安の6gにかなり近づけるのではないかと思います。ちなみに高血圧などがない一般の方では、男性7.5g、女性6.5gが目標と言われていますので、高血圧がなくても家族皆で塩分を摂りすぎないように取り組むのが良いと思います。図1 日本人の1日の食塩摂取量
食品に含まれる食塩量
最近は食品を買うと、裏の表示に食塩量が表記されていることが多いので、皆さんも目にする機会が多くなっていると思います。どんな食品にどのくらいの食塩が含まれているかを示しました(図2)。塩分がかなり多いのは、やはりお漬け物関連です。梅干しは昔ながらのもので20%ほどですが、最近では3%ほどの塩分のものも出ているようです。キムチ、たくあん、ぬか漬けなども塩分が多くなっています。ぬか漬けは5切れも食べると1食の目標の2gに近いような摂取量になってしまいます。お魚でも塩鮭は甘口・中辛・辛口とありますが、甘口も多いと一切れ2.2gも入っていたりします。意外なところではパンです。パンは小麦粉を練って作るときに塩を入れるので、食パン1枚でも1g弱の食塩が入っています。ちくわなどの練り製品、ハム、ウインナーなどにもかなり食塩が含まれています。朝食がパンとウインナー(2本)なら1.8gです。ご飯の場合は塩鮭(一切れ)とお漬け物という組み合わせであっと言う間に2gを超えてしまいます。ですから塩鮭ではなく生鮭を使うとか、ハムエッグやウインナーエッグの場合は、ハムとウインナーの食塩量を考えて卵の味付けは胡椒だけにするなど、足し算と引き算をしていただくのも一つの手ではないかと思います。
図2 食品に含まれる食塩量
料理に含まれる食塩量
次にお料理に含まれる食塩量をみてみましょう(図3)。お米自体には塩分は入っていないのですが、コンビニなどで売っているオニギリにはご飯にも塩が入っているので塩分が多くなりやすいです。お寿司も酢飯を作る際に、砂糖と酢だけでなく塩を使うので、醤油なしでも意外と食塩量が多いです。ですからお寿司を食べる時は、醤油を使う量を控える、あるいは減塩醤油を使うことで食塩量を抑える工夫が望まれます。その他、食塩量が多い料理は汁物や麺類です。味噌汁は1杯で塩分1.5gあります。ラーメンは6.2gですが、汁を全く飲まなければ、図に書いてある食塩量の約半分になります。きつねうどんではトッピングの油揚げにも塩分が含まれます。甘辛の油揚げの代わりに、味の付いていない油揚げにすることで塩分を抑えることが可能です。
図3 料理に含まれる食塩量
調味料の食塩量
調味料に含まれる塩分も問題になってきます。小さじ1杯(5ml)に含まれる食塩量を示します(図4)。小さじ1杯の食塩量は6gなのですが、普通の一般的な醤油(濃口醤油)は0.9gの食塩を含んでいます。薄口醤油は色が薄いので塩分控えめと思いがちですが、料理の色を生かすために色が薄くなっているだけで、塩分は濃口醤油よりやや多くなっています。最近は、色々な減塩醤油も売られていますが、普通の醤油の約半分くらいの食塩量のものが多いようです。味噌汁も、味噌の種類によって塩分量が変わってきます。一方、マヨネーズやトマトケチャップなどは意外と塩分が少ないので、味付けを楽しみながら塩分を控えることができます。図4 調味料の食塩相当量
味付けの工夫
食塩を控えながらおいしく食べるために必要なのが、味付けの工夫です。まず香ばしさの利用です。薄い味付けでも、焼きたて・揚げたての香ばしさでおいしく食べることができます。豚カツも揚げたてならば、ソースをかけなくてもその香ばしさだけで楽しめます。焼き魚では焼きたての香ばしさだけでも食べられますし、酢・レモン・ゆずなどの柑橘類、トマトなどのさわやかな酸味は、塩味にかわる味のアクセントになります。煮物などでは、醤油を減らすのと一緒に砂糖やみりんなどの甘さも減らすと、味のバランスが整いやすくなり、塩味だけを減らしたときの物足りなさが軽減されます。香辛料の利用も一つの手で、スパイス・ハーブ・にんにく・ねぎ・生姜・茗荷・紫蘇・唐辛子などの香味・辛味は塩のかわりに味を引きしめます。さらには、天然のダシ(こんぶ・削り節・干し椎茸など)の旨味は、塩味を引き立ててくれます。ダシのパックを煮出す方が、顆粒のものを使うよりも割と旨味が出やすかったりします。新鮮な旬の食材を使って、素材そのもののおいしさを味わうのも減塩に役立つと思います。食べるときの工夫
食塩を控えるためには食べる時の工夫も大事です。まず、食塩を多く含む食品を避けることです。漬け物や練り物などの加工食品は食塩を多く含むため、量や頻度を少なくすることが望まれます。醤油や調味料などの減塩食品の利用も一つの方法であり、最近では冷凍のうどんやパンなどでも塩分無添加の商品があります。味付けのタイミングも問題で、食べるときに味付けするというのも大事です。下味を付けてから料理すると、味が浸透してどうしても塩分過剰になりがちです。ですから下味はつけずに調理し、食べるときに塩や醤油を表面に少しかけたりして食べましょう。麺類などでは塩分を多く含む汁は残す、味噌汁などの汁物は毎食では無く1日1杯にするのが良いでしょう。
バランスの良い食事
バランスの良い食事のためには、主食、主菜、副菜を毎食揃える事が大事です。主食となるのは米・パン・麺類などの炭水化物です。白いご飯の炭水化物が気になる方は、玄米・雑穀・もち麦などを少し加えると食物繊維も多く摂ることができます。蛋白源となる主菜は、肉や魚が相当します。肉はなるべく脂身の少ない部位を利用しましょう。脂身には先ほどの講演で話しのあった、急性心筋梗塞などの原因となるコレステロールを作るもとになる飽和脂肪酸が多く含まれているからです。魚の脂身は逆にコレステロールを下げる働きがあるので、お勧めです。大豆製品もお勧めです。卵にはコレステロールが多く含まれています。控えた方が良いとか、何個食べても構わないとか諸説ありますが、心臓病予防の観点からは1日1個くらいまでが目安ということになります。副菜としては、野菜・きのこ・海藻類などに食物繊維やビタミン・ミネラルなどが多く含まれています。野菜や海藻類には、塩分を出す働きのあるカリウムも含まれており血圧管理といった点でも重要なので、1日350gは摂りましょう。1食(約100g)の目安は、生野菜では両手一杯、茹で野菜では片手一杯ほどです。汁物は1日1杯程度にして、具沢山がお勧めです。果物や乳製品は1日1回を目安に取り入れると、さらにバランスの良い食事になると思います。 本日お話しした、心臓に良い食事のポイントをまとめました(表1)。
表1 心臓に良い食事のポイント まとめ