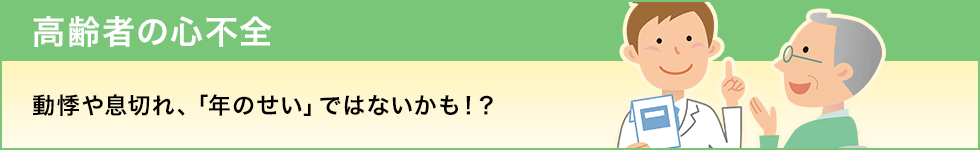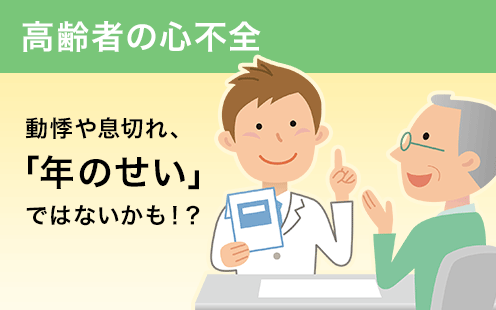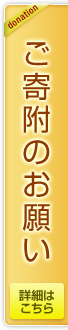講演3:息切れを感じたら、それは心不全かも
心不全ってなんだ?
心不全は、今までお話があった心房細動や急性心筋梗塞を含め、弁膜症や高血圧・糖尿病そして心筋症などあらゆる心臓疾患の先にある状態、つまり終末像です(図1)。かつて心不全イコール心臓が止まること(心停止)を意味していた時代もありましたが、今はそうではありません。心臓は全身の臓器に血液を循環させるポンプであることは皆さんよくご存じと思います。このポンプが拡がりにくくなる、あるいは縮みが悪くなるという機能的な問題が起きて血液を全身にスムーズに循環させられなくなり、症状が出た状態を心不全と呼んでいます。つまり心不全というのは、特定の病名というよりは、いろいろな心臓病の行き着く先の症状ということになります。年を取ること(加齢)も、心臓を硬くするので機能を低下させ、心不全の原因となります。心不全に罹る人の数は多く、がんの推定罹患数が100万人1)なのに対して、心不全では120万人以上2)とされています。心不全は今や先進国の国民病とも言われる状態になっています。日本は世界の中でも超高齢社会であり、長生きすればするほど、心不全に罹る確率が上がることになります。
心不全になって何が困るかというと、心臓のポンプ機能が悪くなるので、当然、体力が落ちて動けなくなってくることです。実は認知機能も低下します3)。また、いろいろな病気(感染症、転倒による骨折など)で入院しやすくなり、年に一度は何らかの理由で入院するようになります。そして最終的には、命が短くなってしまいます。
図1 心不全ってなんだ?
心配な息切れとは?
では心不全発症時の自覚症状は何が多いのでしょうか。フランスにおける心不全入院患者(793人)の調査によると、最も多いのは息切れ(64.7%)で続いて下腿浮腫(足のむくみ、27.7%)でした4)。そしてこのうち約半分の人は、息切れや下腿浮腫が心不全によるものとは入院前に診断した医師ですら気付いていなかったとのことです。皆さんも知識を身につけて、この息切れは心不全の症状ではなかろうかと、医師に相談していただくようになっていただきたい、というのが今日のお話の目標でもあるのです。
寝不足で息切れするというように、理由がはっきりしている息切れは別として、心配な息切れとはどのようもものでしょうか。一つは、いつもの行動に支障が出るような息切れです。たとえば、いつも登ることができている階段が苦しくて登れないというのは、心配な息切れのサインだと思ってください。夜寝ている時に、苦しくて目が覚めてしまう。起きて座っていると楽なのに、また横になると苦しくなる、というのも心配な息切れと言えます。とくに年齢が65歳以上、メタボ(メタボリックシンドローム:腹囲が大きいことに加えて、高血圧・高血糖・脂質異常のうち二つ以上が重複)である、といった方は要注意です(図2)。
図2 心配な息切れとは?
心不全の早期発見・予防にBNPを測りましょう
心不全を疑った場合は、病院で心臓の分泌するホルモンであるBNP(ビー・エヌ・ピー)を測ってもらってください。血液検査で調べます。BNPはBrain Natriuretic Peptideの略で、脳性ナトリウム利尿ペプチドと呼ばれています。その働きは体から余分な塩分と水分を尿として出すことです。このようにBNPは、実は体に良いことをしてくれているホルモンなのです。ただ心不全になってくると、このBNPの分泌が増えてくるという特徴があります。BNPは、心筋が引き延ばされると、それが刺激となって血液中に分泌されるので、心不全の程度や心不全のなり易さを表す指標になります。ここまでのお話をまとめますと、心不全は息切れを起こす病気です、心不全になると介護度が増えてしまうかも知れません、心不全の早期発見・予防にBNPを測りましょう、ということになります(表1)。
表1 心不全は息切れを起こす病気
若く見える人は長生き?!
次に取り上げる話題は、顔が若く見える人(若見え)は顔が老けて見える人(老け見え)よりも長生きだというお話です。デンマークで70歳以上の双子774人を7年間追跡した調査では、若見えのほうが老け見えよりも長生きであることが報告されています5)。欧米での研究で、若見えの人では、血圧が低い・太っていない・尿蛋白がない(腎臓が元気)・血糖が低い・コレステロールが低い・良く動く、という特徴があることがわかっています6)。そして大事なことは、こうした特徴はすべて心不全予防に繋がるということなのです。ですから心不全予防のためには、若見えを目指すことが、一つのポイントになってきます。
血圧コントロール・運動・減塩
続いて心不全予防のために、血圧コントロール・運動・減塩をどこまでやると良いかについてお話ししたいと思います。まず血圧ですが、どこまで下げるべきでしょうか。
日本人約6万7千人を対象とした調査で、中壮年者(40~64歳)と前期高齢者(65~74歳)では上の血圧が120mmHg(水銀柱)、後期高齢者(75~89歳)では130mmHgを超えると心臓病や脳卒中による死亡が増えることが示されています7)。上の血圧が120~129mmHgという値でも、中壮年者と前期高齢者では心臓病や脳卒中による死亡は120mmHg未満の場合より1.8倍ほど高くなっています。中壮年者で上の血圧が180mmHg以上になると、心臓病や脳卒中による死亡は120mmHg未満の場合と比べて約9倍にもなっています。これらは一般的にあまり知られていないデータかもしれません。
血圧と心不全との関連については、上の血圧が120~130mmHgあたりを超えると心不全発症が増えることが米国から報告されています8)。
ですから、120mmHgというのは大事な数字ではないかと思います。このたび改訂版が出た「高血圧管理・治療ガイドライン2025」では、降圧目標を家庭血圧で上が125mmHg未満、下が75mmHg未満としています。しかし、きっちり125mmHgというのはなかなか難しいので、120mmHgを目標にしていただくのが良いのではないかと思います。そのためには生活習慣の改善も大事ですが、やはり早めに血圧を下げる薬を飲むのが得策ではないかと思います。
続いて運動についてです。運動不足は心不全を発症しやすいことが、運動量と心不全発症リスクの関係を調べたスウェーデンの研究(Swedish National March Cohort)で報告されています9)。また同コホートでは、「スタスタ歩き1時間」10)で、心不全発症リスクが低下することも示されています。しかし実は、「スタスタ歩き30分」でも、結構、リスクが減っています。30分を朝・昼・晩と分けて歩いても構いません。会話するには少し息が上がるかな、といったくらいのペースで、自分なりの「スタスタ歩き」をしていただけたらと思います。現状では皆さん運動不足で、65歳以上の日本人約40%が、運動不足により心不全を発症しやすい状態にあるようです。
最後は減塩に関するお話です。塩分を取るとどのくらい血圧が上がるかという具体的なデータをご紹介します。6グラムの食塩入りスープと食塩の入っていないスープを飲んだ場合の血圧の変化を調べたものです。6グラムの食塩入りスープというのは、大体カップラーメンの汁を全部飲んだ場合です。そうすると、上の血圧は14mmHg、下の血圧は8mmHg上昇して、これが食後3時間まで続いたというのです11)。塩分を一気に取りすぎると、良くないことがわかります。逆に塩分摂取を減らすと(約9.5グラムから8年後に約8.1グラム)、血圧が下がり(上の血圧は約2.7mmHg低下)、虚血性心疾患や脳卒中による死亡が減る(各々40%、42%減少)といった英国からの報告もあります12)。
減塩が良いといっても、塩分を細かく計算しながら食べるのはなかなか厳しいと思います。そこで、意識するだけで減塩になるかもしれない、というデータをお見せしたいと思います。この報告では、減塩を意識していない場合(89例)の食塩摂取量は10.6±4.0g/日だったのに対し、減塩を意識している場合(271例)は9.4±3.8g/日でした13)。減塩を意識するだけで約1.2g/日減っています。儲けものですので、是非、減塩を意識して頑張ってみてください。
今日のお話しは以上です。まとめをお示しします(表2)。
表2 今日のまとめ
2)Circulation Journal 2008年 72巻 489-491頁
3)European Journal of Heart Failure 2017年 19巻 253-260頁
4)Clinical Cardiology 2021年 44巻 1144-1150頁
5)British Medical Journal 2009年 339巻 b5262
6)Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2024年 121巻 e2308812120
7)Hypertension Research 2012年 35巻 947-953頁
8)Heart 2011年 97巻 1304-1311頁
9)Circulation Heart Failure 2014年 7巻 701-708頁
10)Journal of the American College of Cardiology Heart Failure 2018年 6巻 996-998頁
11)Kidney International 2012年 81巻 407-411頁
12)British Medical Journal Open 2014年 4巻 e004549
13)Hypertension Research 2004年 27巻 243-246頁