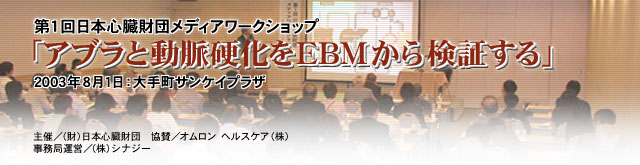
 |
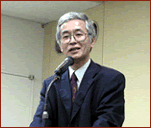 |
 |
| 筑波大学臨床医学系内科教授 山田 信博氏 |
東京都多摩老人医療センター 院長 井藤 英喜氏 |
虎の門病院院長 山口 徹氏 |
| 山口氏: | 井藤先生に「食事と血清脂質の関係について」、山田先生に「高脂血症治療と動脈硬化」をテーマにご講演いただきました。会場の皆さんからのご質問を受けたいと思います。 |
| 会場より: | ガイドラインでは高脂血症の食事療法は2段階に分かれていますが、例えばコレステロールの摂取を1日300mg以下にしなさいというような具体的な指導をされるのですか。また、指導は誰がするのですか。 |
| 井藤氏: | 食事療法では具体的な数値を目標にしないと患者さんも理解しにくいので、具体的な数値を示します。どういう食品の組み合わせであれば、1日のコレステロール摂取量を300 mg以下にできるかといった献立の指導は栄養士さんの仕事になります。逆に、患者さんに食事内容をメモしてきてもらい、それを見てコレステロールの摂取量が多ければ、この食品を減らしてほしいといった指導も行います。 |
| 会場より: | 高コレステロール血症と高トリグリセリド血症では、どちらがより強く動脈硬化を促進するのですか。 |
| 井藤氏: | 高トリグリセリド血症が本当に動脈硬化の危険因子であるかについては、まだ議論があるところです。一方、高コレステロール血症が動脈硬化の危険因子であることは確実であり、その意味ではランクが違うといってもよいと思います。 |
| 山口氏: | 有酸素運動が動脈硬化を予防するという話は、どの程度のエビデンスがあるのでしょうか。また、食事療法との比較という点ではどうなのでしょうか。 |
| 井藤氏: | 食事療法単独群、運動療法単独群、食事+運動療法群を比較したRCTがありますが、この試験で血清脂質や体重といった代謝マーカーからみて結果が最もよかったのは食事療法です。一方、ある時期の運動量と、その後10年ぐらい追跡したときの動脈硬化性疾患の発症率や死亡率をみたコホート研究では、運動をした群で発症率が低いというデータが出ています。また、脳梗塞の発症に関しては、1日20分程度のウォーキングでも効果があるという成績もあるので、運動が動脈硬化の予防に効果があるのではないかということが示唆されているのではないかと思います。 |
| 山田氏: | 血液検査でみると、運動はトリグリセリドを下げHDL-Cを上げます。一方、運動は筋肉を鍛えてインスリン抵抗性を改善しますから、耐糖能や血圧にもよいはずで、そういう意味で動脈硬化の予防によいというデータが出てきているのだと思います。 |
| 会場より: | 山田先生のお話では、抗酸化ビタミンは動脈硬化の予防あるいは治療に効果がないということでしたが…。 |
| 山田氏: | 心血管イベントの抑制をエンドポイント(評価項目)にした研究では、抗酸化ビタミンの効果はポジティブには出てきません。しかし、例えば薬剤としてのビタミンEと食品中のビタミンEには異なる部分もあるようです。また、大量に摂取すると体内で活性酸素が増えると指摘している研究者もいます。ですから、なかなか難しいというのが率直な印象ですが、酸化には病的な意義があるというデータも多いので、食品に含まれる抗酸化物質をうまく利用したらよいのではないかと思っています。 |
| 井藤氏: | 赤ワインや玉ねぎなどに多く含まれるポリフェノールについては、前向きコホート研究で摂取量が多いほど虚血性心疾患の発症が少ないというデータが出ています。しかし、抗酸化ビタミンについては賛否両論です。日本動脈硬化学会のガイドラインでは食品からの摂取を推奨していますが、ガイドラインはそのときどきで変わっていきますから、将来消える可能性もあります。また、欧米のデータでは蛋白源として肉より魚のほうがよいといわれていますが、日常的に魚をよく摂取している日本人にもっと魚肉を取りなさいというのは、本当に意味のあることなのだろうかという疑問もあります。 |
| 山田氏: | よくフレンチパラドックスといわれますが、ワインですから、つまりアルコールですから肝機能は悪くなります。肝臓はアルブミンをはじめ多くの抗酸化物をつくっていますが、そういう物が減ってきますし、肝障害が起これば酸化物をうまく処理できなくなります。井藤先生が賛否両論といわれましたが、その賛否をよく見極めることが重要だと思います。 |
| 会場より: | 生体の機能維持に必要なLDL-Cは50mg/dLというお話でしたが、例えばTCでいうとどの程度のレベルになるのですか。 |
| 山田氏: | 130〜140mg/dLぐらいです。 |
| 山口氏: | LDL-Cを強力に下げる薬剤の登場によりTCを140mg/dLまで下げることも不可能ではないかもしれませんが、逆にそんなに下げてよいのかという疑問もあります。 |
| 山田氏: | 下げることが悪いのではなく、下げる方法が安全かどうかが問題です。薬剤を使うわけですから…。一方、TC 140〜220mg/dLまでは動脈硬化のリスクは徐々にしか上がりませんから、コレステロールを下げる意味がどれだけあるのか、効率と安全性についても考える必要があります。 |
| 会場より: | 高LDL-C血症が持続する場合の第2段階の食事療法で、飽和脂肪酸/一価不飽和脂肪酸/多価不飽和脂肪酸の摂取比率が3:4:3ということでしたが、飽和脂肪酸が悪いということですから、摂取比率を下げたほうがよいのではないかと思いますが…。 |
| 井藤氏: | 確かに飽和脂肪酸の比率をもっと下げたほうがよいという提案もあります。しかし、飽和脂肪酸の比率を半分にすると、ほとんど肉を食べないことになり、それでよいのだろうかという議論もあります。日本人にとって肉、魚、それから一価不飽和脂肪酸を含むオリーブ油や紅花油を適度に摂取できる組み合わせということで、今回の比率になったわけです。 |
| 会場より: | 最近、米国食品医薬品局(FDA)が食品に含まれるトランス型脂肪酸量の表示義務化を発表しましたが、これはショートニングなどに含まれているものですか。 |
| 井藤氏: | そのとおりです。トランス型脂肪酸はLDL-C値を上昇させますが、日本人の摂取量はそれほど多くないため、普通の食生活をしている限りにおいては特に問題はありません。しかし、米国人はあらゆるところで油を使うので、その摂取量は日本人に比べて数倍多いです。ですから、その摂取を減らす努力が必要ですし、減らせば効果もあるでしょうね。 |
| 会場より: | 高脂血症の患者さんでは高血圧や糖尿病を合併するケースが多いと思われますが、経口血糖降下薬あるいは降圧薬でスタチン系薬剤との組み合わせの悪い薬剤はありますか。 |
| 山田氏: | 薬物相互作用に注意しますが、スタチン系薬剤との併用で問題を生じるような経口血糖降下薬や降圧薬はないと思います。 |
| 山口氏: | 時間がまいりましたので、第1回メディアワークショップを終了させていただきます。今後も時々ワークショップを開催して、コミュニケーションを図れたらと考えております。本日は大勢の方のご参加をいただき、まことにありがとうございました。 |
| ▲PAGE TOP |